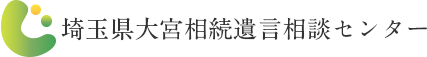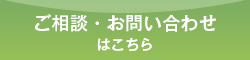遺言書
被相続人が自身の死後、財産や権利などで相続人同士のトラブルが起きないように民法の規
定にのっとって最終的意思表示を記した書面を「遺言書」といいます。
遺言書では法定相続分とは異なる相続割合や遺産分割の方法、法定相続人を相続人から廃除すること、法定相続人以外の特定の人物に財産を譲り渡すといったことを決めることができます。
簡単に思える遺言書ですが、民法の規定にのっとって書かれていない遺言書は法的な効力はなく無効となりますので作成する際は注意が必要です。
遺言書の種類

遺言書は大きく分けて、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があり、種類によって作成方法や検認の有無などが異なります。必要な要件を満たしていないと、せっかく書いた遺言書が無効になってしまうこともありますので、作成にあたっては専門家に相談するのがいいでしょう。
自筆証書遺言
遺言者本人が自筆で全文、日付・氏名を書いた後、署名押印する遺言書です。遺言書の存在を秘密にすることはできますが簡単に作成できてしまうので、後々になって偽造を疑われる可能性があります。自筆証書遺言を保管する人は、相続が開始した後に家庭裁判所で検認の手続きをとる必要があります。
※代筆・パソコンやワープロ、タイプライターなどで作成した自筆証書遺言書は本人が書いたものであるか判断が難しいため、また録画やビデオで作成された遺言書は、音声や映像の編集を行うことが可能なので無効となります。
秘密証書遺言
遺言書の内容を誰にも知られたくない場合に作成する遺言書。作成そのものは自筆証書遺言と変わりありませんが、秘密証書遺言は代筆・パソコン・ワープロでの作成も有効となっています。(※ただし、署名は自筆であること)
署名押印した遺言書を封筒に入れ、押印した印鑑と同じ印鑑で封を閉じます。証人2人以上と一緒に公証役場に出向き、遺言書を提出します。公証人に自身の遺言書であることを申述し、公証人が提出日付と遺言者の申述を封書に記載したのち、遺言者本人、証人、公証人が封書に署名押印し完了となります。
公証人が関与するので遺言書の存在が明確にすることができる一方、遺言書の管理を自分自身で行う必要があるので、紛失や改ざん、破棄されるおそれがあります。
公正証書遺言
証人2人が立ち会いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、その内容を公証人が筆記した後に遺言者・証人に読み聞かせます。遺言者と証人が筆記が正確なことを確認したら各自が署名押印し、公証人が方式に従ったものであることを付記してから署名押印して作成します。他の遺言と違い偽造される可能性は低いものの、遺言の内容を話すため秘密にすることができません。なお、家庭裁判所の検認は不要です。
遺言書は相続に関するトラブルを防ぐための有効な手段といえます。相続人以外に財産を譲りたい場合(内縁の妻がいる場合や自身が独身の場合など)や、相続人の間で優劣を付けたい場合(同居の子と別居の子がいる・認知した隠し子がいるなど)は円滑に相続の手続きが進めるためにも遺言書の作成を検討しましょう。
ただし、すべてのケースが認められるというわけではなく、中には無効となってしまうケースがあります。その代表的なのが「遺留分」と呼ばれるものです。
遺言書を残したほうがいいケース

相続には様々なケースがあり、円滑に手続きが進むケースがあれば、争いに発展しやすいパターンもあります。相続財産の内容や被相続人の家族構成・環境など、特にトラブルが起きやすいケースがありますので、以下に該当する場合はぜひ遺言書の作成をご検討ください。
相続人以外に財産を譲り渡したいケース
| 子の妻に相続させたい場合 | 内縁の妻がいる場合 |
|---|---|
| 子供の妻から介護をされている場合でも、子供の妻は他人という扱いになるため、相続させたい場合には遺言書が必要です。 | 内縁の妻は配偶者にはならないため、相続させたい場合は遺言書に書いておく必要があります。 |
| 妻に連れ子がいる場合 | 独身の場合 |
| 妻の連れ子は養子にしない限り他人扱いになるため、相続させたい場合は遺言書に書いておく必要があります。 | 独身で、親も兄弟も亡くなっている場合、遺言書がないとすべての財産が国に寄付されることになります。 |
相続人間で優劣をつけたいケース
| 特定の子に多く財産を与えたい場合 | 同居の子と別居の子がいる場合 |
|---|---|
| 法定相続分では子は全員同じ扱いなので、特定の子に多く財産を譲り渡したい場合は遺言書が必要です。 | 法定相続分では子供は全員同じ扱いなので、同居の子に多く財産を譲り渡したい場合は遺言書が必要です。 |
| 後継者を指定して事業を継承させたい場合 | 認知した隠し子がいる場合 |
| 後継者以外の人に株式や事業用財産を相続させないためには、遺言書が必要になってきます。 | 子同士の争いが起こるおそれがあるため、ご自分との関わりや子同士の関わりなどに配慮して、最適な配分を記した遺言書を作成するのがいいでしょう。 |
相続財産の内容などが特殊なケース
| 相続財産の大半が自宅のケース | 親の土地の上に子の建物がある場合 |
|---|---|
| 自宅を売却して分ける以外の遺産分割の方法がなくなってしまいます。 | その子供が土地を相続することになると、他の兄弟に対して賠償金を支払わないといけないことになります。 |

遺言書はトラブルを防ぐための有効な手段です。ぜひ円滑・円満な相続のため、有効に活用していただきたいと思います。なお、上記のように遺言書では様々なことを定められますが、たとえ遺言書に記したとしても無効になってしまうケースもあります。その代表的なものである「遺留分」について、以下で詳しく見ていきましょう。
遺留分とは
一定の相続人が最低限相続できる財産のことを「遺留分」といいます。遺言者は遺言書を作成すれば法定相続人以外に財産を譲ることも可能ですが、遺言書どおりに執行されると、残された家族の生活が立ちゆかなくなってしまうおそれがあります。
相続人(配偶者・子供・父母のみ。兄弟姉妹は含みません)にとって不利益な事態になることを防ぐためにも、民法では最低限相続できる財産を「遺留分」として保証しています。相続人が「遺留分を侵害された」と遺留分減殺請求権を行使すると、侵害している者は侵害している分の財産を遺留分権利者に返還しなければなりません。
遺留分に抵触する内容が遺言書に記載されていた場合でも、遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由です。そのため、相続人が自身の遺留分の範囲まで財産返還を請求することができる「遺留分減殺請求」を行使しなければ遺言書は有効となり、遺言書に記された内容のとおりに執行されます。
ただし、遺留分権利者が相続の開始・減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年、もしくは相続開始から10年経過した場合は消滅時効となり、遺留分減殺請求権を行使することはできなくなります。
こういった争いを防ぐためにも遺言者は、遺留分も考慮した上で遺言書を作成しなくてはなりません。

遺留分に抵触する遺言書があっても、それが当然に無効になるわけではありません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは、あくまでも相続人の自由。相続人が、「遺留分減殺(げんさい)請求権」という権利を行使しない限り、その遺言書は有効な遺言書として効力を有するのです。
遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害している者は、侵害している分の財産を遺留分権利者に返還しなければならなくなります。